ar
الأسماء في صفحات التنقل


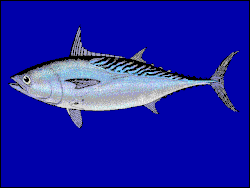

 分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 綱 : 条鰭綱 Actinopterygii 目 : スズキ目 Perciformes[1] 科 : サバ科 Scombridae 属 : スマ属 Euthynnus
分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 綱 : 条鰭綱 Actinopterygii 目 : スズキ目 Perciformes[1] 科 : サバ科 Scombridae 属 : スマ属 Euthynnusスマ(須萬、須万、学名:Euthynnus affinis)は、スズキ目サバ亜目サバ科スマ属に分類される海洋生条鰭類の1属。インド太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布する大型肉食魚で、食用にもなる。
学名(ラテン語名)のうち、属名の由来は、ギリシャ語による合成語「eu(=good、良)+thynnos(=tuna、マグロ)」である[3]。
日本語の地方名としては、ワタナベ(千葉県)、スマガツオ(東京都)、キュウテン(八丈島)、ホシガツオ(高知県)、ヤイト・ヤイトガツオ(西日本各地)、ヤイトマス(和歌山県)、ヤイトバラ(近畿地方)、オボソ(愛媛県愛南町)などがある。
英語名は、Kawakawa、Kawa kawa、Black skipjack、Black skipjack tuna、Eastern little tuna、Island skipjack、Little tuna、Little tunny、Mackerel tuna、その他多数が存在する[3][1]。
中国語では「巴鰹」(バージエン)と称する。台湾語では「煙仔魚」(イエナヒー)、「三點仔」(サムディアマー)などと称する[4]。
成魚は、全長1メートル、体重10キログラムに達する[5]。体型はカツオなどと同様の紡錘形で、鱗は眼の後部・胸鰭周辺・側線周辺にしかない。カツオと違って腹側に縞模様は出ず、背中後半部に斜めの黒い帯模様が多数走る。また、生体では胸鰭の下に1 - 7個の黒い点が出るのが特徴で、西日本での呼称「ヤイト」はこの黒点を灸の跡(高知では星)になぞらえたものである。ただしこの黒点は死ぬと消えてしまう。全長10センチメートル程度の幼魚は細長い体型で、黒っぽい横帯模様が約12条ある。他の類似種には、ヒラソウダ、マルソウダ、ハガツオなどがいるが、スマの成魚はこれらより体高が高い。
カツオほどの大群は作らず、単独か小さな群れで行動する。また、沿岸性が強く、若魚は内湾に入ることもある。食性は肉食性で、魚、甲殻類、頭足類などを捕食する。
日本の本州中部以南から、ハワイ、オーストラリア北部、アフリカ東岸まで、西太平洋からインド洋にかけての熱帯海域および亜熱帯海域に広く分布する。
カツオ、マグロ、シイラなどを狙った釣りや延縄で漁獲されるほか、定置網などの沿岸漁業でも混獲される。フィリピン、マレーシア、パキスタン、インドなどでは重要な漁獲対象となっており、1990年代には年間10万トン前後が捕獲された[7]。
身はカツオに似た赤身で、日本では刺身、焼き魚などで食べられる。台湾では刺身、スープ、鉄板焼などに利用されている。食用以外にマグロやカジキなどの釣り餌として使われることもある。2キログラムを超える魚は1キログラムあたり1500円以上の高価で取引される[8]。マグロと違って小型であることから、既存の魚の養殖施設を活用でき、「味がマグロに似ており、クロマグロの代替魚としての需要を見込み」[9]、愛媛県と和歌山県では養殖の研究が開始され、初の越冬も成功した[10]。現在の課題は知名度の低さである[11]。なお、愛媛、和歌山ともブランド名が決まり、愛媛は「伊予の媛貴海」(ひめたかみ)[12]、和歌山は「海の三ツ星」となった[13][14]。